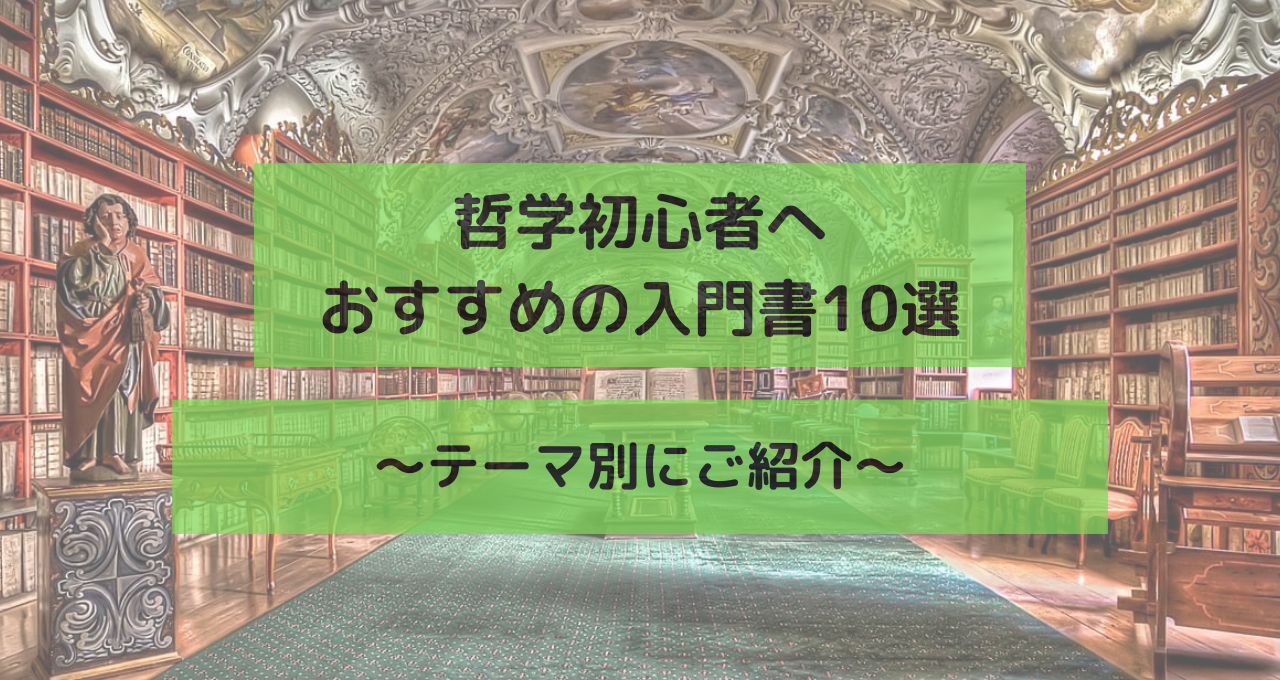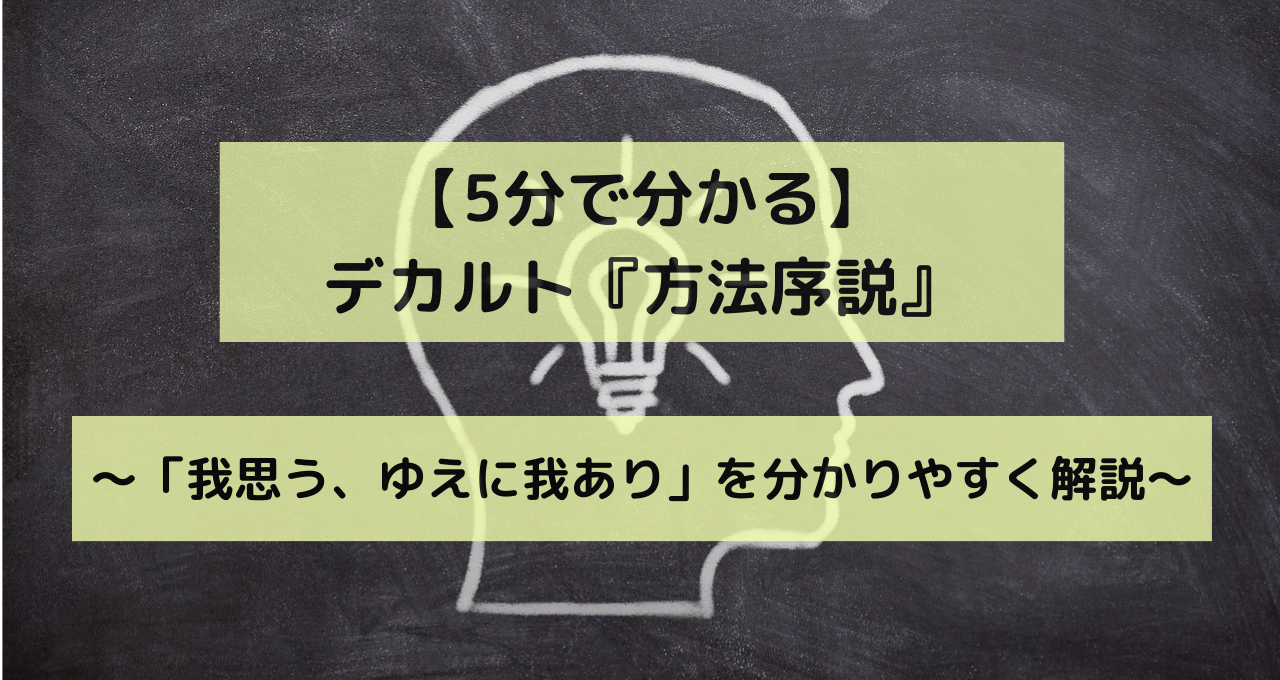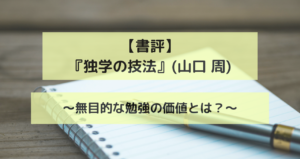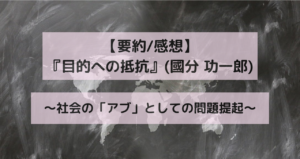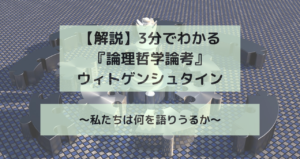誰もが知っていて、とっつきやすさNo.1の哲学者デカルト。
そんなデカルトの思想を押さえるための必読書が『方法序説』です。
解説を除くと100ページ余りと読むハードルも低いため、日本でも多くの人に読み継がれてきた哲学の名著。
しかし、哲学を全く知らない状態で挑むと、いまいち本書の意義が掴めないのもまた事実です。
✔ デカルトがどうして「近代哲学の父」と言われるのか?
✔ あの有名な「我思う、ゆえに我あり」は何がすごいのか?
この記事では、『方法序説』の要点と哲学史上の意義を解説しながら、これらの疑問に答えていきます。
「近代哲学の父」デカルト

「我思う、ゆえに我あり」という言葉とあわせて、誰もが知る哲学者デカルト。
実は、デカルトは数学者でもあり、中学の数学で必ず登場するx軸、y軸の値を平面上に図示する「座標」を発明するなどの功績を残しています。
また、哲学者としては合理主義を切り開いた「近代哲学の父」とも称され、西洋の哲学者TOP5を挙げろと言われたら確実に入るであろう重要人物です。
合理主義と経験主義
合理主義と対比されるのが経験主義。
この2つは、16世紀頃~18世紀カントまでの哲学の二大潮流として、近代哲学をけん引した思想です。
- 知識は「理性」から得られる
- 合理的思索を重ねて知識を獲得していく
- スピノザ、ライプニッツ など
- 知識は「経験」から得られる
- 経験や実験を重視し知識を獲得していく
- ロック、ヒューム など
経験主義は、私たちの視覚や触覚などの感覚から得た経験こそ唯一確実なのだから、理性ではなく経験を重視し世界を解き明かそうとします。
一方で合理主義は、人間の「理性」を用いて合理的に世界の真理に到達できると考えます。
そして、この合理主義の祖として、人間理性の可能性を見出したのがデカルトなのです。
5分で分かる『方法序説』
デカルトが人間理性の可能性を見出した、とはどういうことなのか?
それを理解するために読むべきなのが、1637年に出版された『方法序説』です。
実は本書は「序説」とあるように、デカルトが発表した科学論文に付け加えられた序文なのです。
正式なタイトルは、『理性を正しく導き、学問において真理を探究するための方法の話[序説]。加えて、その方法の試みである屈折光学、気象学、幾何学』
何やら長いタイトルですが要するに、最初に「理性を用いて真理を探究する方法」を説明した上で、その方法で研究しましたよ、というわけです。
真理探究の4つの規則
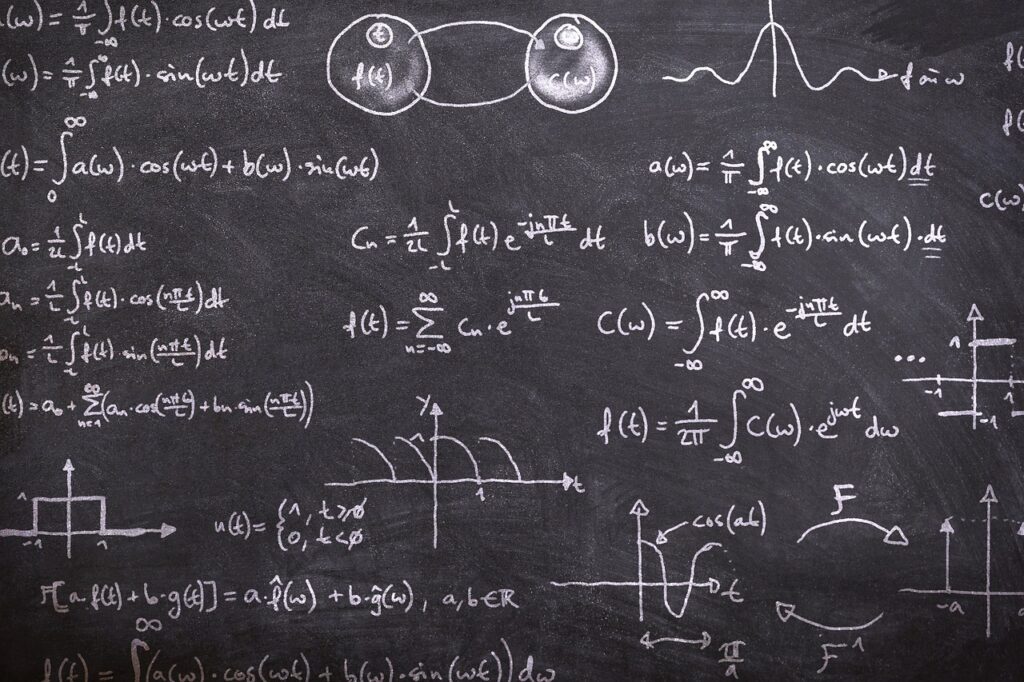
デカルトは本書の中で、真理を探究するための4つの規則を提示します。
速断と偏見を避けて、少しでも疑わしいものは排除する。
いきなり大きな問題を解こうとするのではなく、シンプルな問題に分割して考える。
単純なものから、少しずつ階段を昇るように、複雑な認識に達する。
現代風にいえば、MECE(漏れなくだぶりなく考えるためのフレームワーク)的な思考ができているかチェックすること。
現代のロジカルシンキングの本に出てきてもおかしくない内容ですね。
デカルトはこれらの規則を、代数学と幾何学分野に適用し、複雑だと思われた多くの問題を解くことに成功しました。
「我思う、ゆえに我あり」
さらに、デカルトはこの4つの規則を用いた検討が他の学問にも通用すると考え、すべての学問の基礎である「哲学」に適用しようします。
哲学の土台になる「第一原理」とは?
私たちが算数・数学で習う図形(ユークリッド幾何学)には、「三角形の内角の和は180°になる」といった数多くの定理があります。
実はこれらすべての定理は、「任意の2点が与えられたとき、それらを端点とする線分を引くことができる。」といったような、ユークリッド幾何学の5つの公理から導き出されるものです。
つまり、公理さえ定まってしまえば、それを土台に誰もが納得する共通の壮大な体系を作り上げることができる。
というわけでデカルトは、まずはすべての哲学の土台になる「第一原理」を見つけようとするのです。
方法的懐疑
ほんの少しでも疑いをかけるものは全部、絶対的に誤りとして廃棄すべきであり、その後で、わたしの信念のなかにまったく疑いえない何かが残るかどうかを見きわめねばならない
デカルト(谷川多佳子訳)『方法序説』岩波文庫
しかし、「第一原理」を見つけるのは、相当な責任感を伴います。
なぜなら、「第一原理」が後から「実は間違っていました」となれば、その上に建てられたすべての体系は崩れ去ってしまうからです。
デカルトは、この責任重大な仕事を行うために、「方法的懐疑」という方法を取ります。
- 感覚は私たちを欺くことがある
- 推論も誤らないとは限らない
- すべては夢かもしれない
特に3つ目なんて言い出したら元も子もないような想像ですが、とにかくデカルトは疑いつくす。
どんな懐疑にも耐えることができるものこそ、「絶対的な真理」となり得るからです。
ちなみにこのデカルトの疑いは、「方法としての」懐疑です。
決してデカルトは、「すべては疑えるから確実ではない!」という主張がメインの懐疑論者ではないことに注意が必要です。
「我思う、ゆえに我あり」への到達
わたしは、それまで自分の精神のなかに入っていたすべては、夢の幻想と同じように真ではないと仮定しよう、と決めた。しかしそのすぐ後で、次のことに気がついた。すなわち、このようにすべてを偽と考えようとする間も、そう考えているこのわたしは必然的に何ものかでなければならない。
デカルト(谷川多佳子訳)『方法序説』岩波文庫
たとえ、目の前のことが夢だろうと、誰かに見せられている幻想だろうとも、夢を見る自分、幻想を見せられる自分が存在しなければならない。
このようにしてデカルトが辿り着いた哲学の第一原理こそ、「我思う、ゆえに我あり」です。
デカルトといえばこの言葉だけが独り歩きしていますが、ここで重要なのが「心身二元論」という考え方。
わたしは一つの実体であり、その本質ないし本性は考えるということだけにあって、存在するためにどんな場所も要せず、いかなる物資的なものにも依存しない
デカルト(谷川多佳子訳)『方法序説』岩波文庫
デカルトの「我思う、ゆえに我あり」は、私の存在の根拠を「考えること」に求めています。
つまり、物質的なものとしての「身体」と「考える精神=理性」を明確に区別した上で、「理性」を「身体」よりも優先するものとして上位に置いた。
「我思う、ゆえに我あり」の西洋哲学史的な意義はここにあります。
人間理性の確立

こうして見事に哲学の第一原理を打ち立てたデカルトですが、ここから歩みは腑に落ちない方向に進みます。
わたしは、自分の持たないいくつかの完全性を認識しているのだから、わたしは、現存する唯一の存在者ではなくて、他のいっそう完全な存在者が必ずなければならず、わたしはそれに依存し、わたしが持つすべてのものはそこから得たはずだ、と。
デカルト(谷川多佳子訳)『方法序説』岩波文庫
「不完全」な存在である人間が、どうして「完全」な存在について考えることができるのか?
この問いに対してデカルトは、次のように説明しようとします。
「それは不完全な人間は、完全な存在=神のおかげで存在しているからだ」
現代の常識では到底納得しがたい回答ですが、ここには「神」が絶対的な存在者として君臨していた、中世のスコラ哲学の影響から抜け出せていないデカルトが垣間見えます。
にもかかわらず、これこそ西洋哲学史上の重要な転換点であることは忘れてはいけません。
中世スコラ哲学では、真理は「絶対的な存在者=神のみぞ知る」という考え方でした。
しかしながらデカルトは、「神」を媒介として、人間の「考える精神=理性」は明晰に物事を認識できる、と考えたわけです。
つまり、真理の探究は人間にも可能であると。
神を後見人としてではありますが、哲学において人間の「理性」を見出し、その無限の可能性を確立したことこそ、デカルトが「近代哲学の父」と称される所以なのです。
終わりに
今回は、デカルトの『方法序説』の内容と、その哲学史的な意義を簡単に解説しました。
哲学書は、時代の文脈に照らし合わせて読む必要があります。
私は本書を初めて読んだとき、哲学について全くの無知で、「”我思う、ゆえに我あり”なんて当たり前じゃないか、これの何がすごいんだ?」と感じた記憶があります。
結論だけ切り取ると大したこともないと感じてしまう主張が多いのが哲学。
しかし、その結論にどんな時代背景があり、どんな文脈で発せられたが少しでも分かると、その面白さが分かってきます。
「哲学書をもっと読んでみたい」という方は、初心者へおすすめの入門書を紹介していますのでぜひご覧ください。