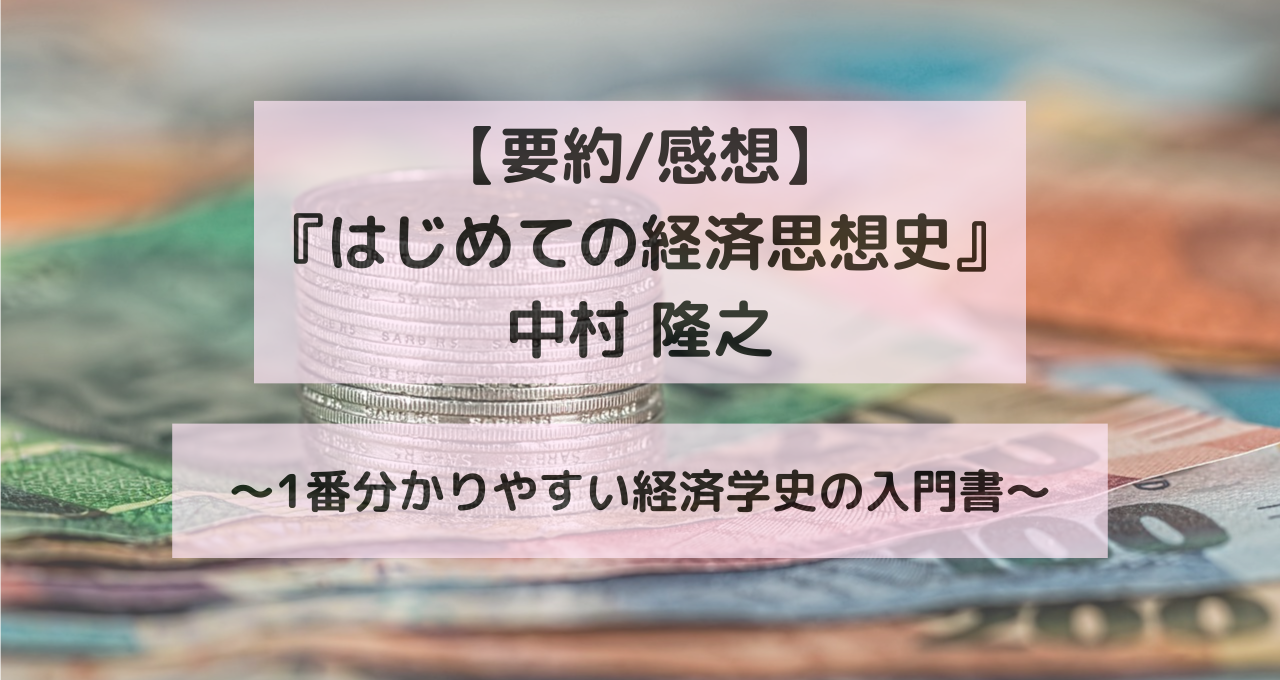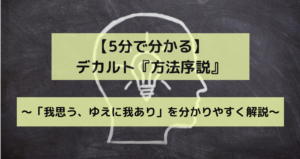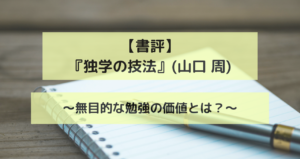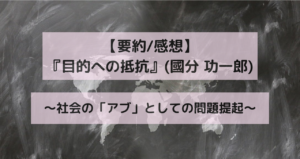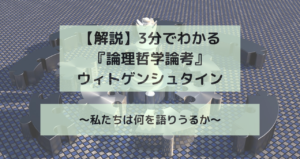今回は、経済学史の入門におすすめ『はじめての経済思想史 アダムスミスから現代まで』を紹介。
経済学は、他の社会科学と同様、その歴史は比較的浅く、18世紀のアダムスミスに端を発しています。
しかし、今や日本の文系分野において法学部と並ぶ花形的ポジション(※個人の偏見です)を確立しており、文系の中心的存在を担う学問といっても過言ではありません。
一方で、経済学といえば数学を用いるというイメージもあり、文系の私からすれば、なかなかその思想の全容が掴みづらいというのが正直な印象でした。
本書は、そんな経済学の歴史の流れを理解するのに最適な1冊です。
記述はとても明晰で、前提知識も必要ありません。
今回は、本書の内容に沿って、経済思想史の流れを解説していきます。
『はじめての経済思想史』はどんな本か?
○○学とつくものには、たいてい共通の主題やテーマ、問いが存在します。
それでは、経済学の主要な「問い」とは何でしょうか?
本書は、この疑問に対して、一言で答えてくれます。
どうすればよいお金儲けを促進し、悪いお金儲けを抑制できるか、である。
中村隆之『はじめての経済思想史 アダムスミスから現代まで』(講談社現代新書)より
とてもシンプルかつ、興味深い答えですね。
もう少し掘り下げると、経済学の歴史とは、悪いお金儲けが力を持つたびに、それに対抗する手段を講じていくための思想の展開である、というのが著者の解釈です。
悪いお金儲けというのは、法律的な合法/違法の話にとどまりません。
資本主義経済はいかようであれば、多くの人に利益をもたらすか、といった根本的な問いから考えるのが経済学なのです。
本書は、そんな経済学の思想史を、その始まりであるアダム・スミスを中心に位置づけます。
そして、その後の経済学者の思想を、アダム・スミスに照らし合わせながら1本のストーリーとして提示してくれます。
今回は、そのストーリーを、かいつまんで見ていきましょう。
経済思想の本流
本書では、経済学の歴史の中で、アダム・スミスを起点したとして、ミル、マーシャル、ケインズを「経済思想の本流」として位置付けます。
アダム・スミスは、各自がお金儲けを追求する自由競争市場を肯定しましたが、儲けることができれば何でもあり、という極端な思想の持主ではありません。
どうしても格差が生じる資本主義と道徳性・公平性がいかに両立するかを、考えたのがアダム・スミスなのです。
そして、アダム・スミスが考えていた道徳性・公平性の条件を、時代の移り変わりに合わせてアップデートさせていったのが、ミル、マーシャル、ケインズであり、それこそが「経済思想の本流」であるというのが本書の主張です。
アダム・スミス

アダム・スミスは、18世紀初頭スコットランド生まれの経済学者です。
アダム・スミスの思想の関心は、「国の豊かさ」についてでした。
当時、欧米列強はこぞって海外進出を行い、植民地経営での海外事業から大きな利益を上げる「重商主義」こそが国を富ませるために必要とされていました。
しかし、アダム・スミスは、国の外からの富ではなく、国民の労働により豊かな財・サービスが生み出せる国こそが豊かであると考えます。
そのためには、国内の労働生産性の向上が鍵であり、「分業」こそが労働生産性を高めると考えました。
というのも、各々が専門的な仕事を行い、その成果として市場へ財・サービスを提供する中で、才能・スキルを自由に伸ばすことができるため、それが社会全体の豊かさに繋がるからです。
だからこそ、アダム・スミスは、各自が努力して自由に才能を伸ばし、その成果を受け取る自由競争市場を肯定したわけです。
見えざる手
そして、アダム・スミスが考えた豊かな国のもう1つ条件は、資本主義が適切に作用することです。
実際に財・サービスを生産するために投入されるのは、国民の労働力だけではありません。
資本主義社会においては、資本や土地を投入し、それに対して「利潤」「地代」といった報酬が与えられるようになっています。
現代社会において、株の配当や不動産収入だけで暮らしていける大金持ちがいる一方、私たちが労働力の投入で得られる収入はたかが知れています。
どう考えても資本主義社会は、公平性を欠いているわけです。
しかし、それでもアダム・スミスは、自由競争の資本主義経済を肯定しました。
それを説明するのが、あの有名な『国富論』の「見えざる手」です。
自分が利益を最大化したい資本や土地の所有者は、一番儲かるところにそれらを投下することになります。
一番儲かるところとは、需要が高い事業です。
そうすると、たとえ資本、土地の所有者が自己利益の追求しか考えていないとしても、それは結果的に多くの人が求めている財・サービスが提供されることになります。
つまり、所有者の自己利益の追求が、結果として公共の利益の推進に繋がり、その国は豊かになる。
この機能のことをアダム・スミスは、「見えざる手」と呼んだわけです。
つまり、自由競争市場によって各人の能力を発揮させ、「見えざる手」によって資源をよい方向へ向けることで、豊かな国が実現できる。
だから資本主義経済はおおむね問題ない、というのがアダム・スミスの結論です。
資本主義の道徳的条件
著者は、アダム・スミスの主張から、「資本主義の道徳的条件」を3つ提示します。
中村隆之『はじめての経済思想史 アダムスミスから現代まで』講談社現代新書
- 自由競争市場がフェア・プレイに則った競争の場であること、特に資本を動かす人間がフェア・プレイを意識する人間であること
- 資産を事業に活用するのではなく、貸し出して利益(利子・地代)を得ようとする場合、その行動が資産をよい用途に向けていく助けになり、全体の富裕化を促進すること
- 強者が弱者を支配せず、相互利益の関係を結び、弱者の能力も活かさせること
これらは、資本主義経済が健全に国を富ませるために必要不可欠な要素として、その後の経済学の基準となります。
そして、この後展開される思想は、時代に変化によって、これらの条件が満たされない現状への処方箋を各経済学者が提示する営みに他なりません。
つまり、「経済思想の本流」とは、「アダム・スミスがいった条件が成立していないけどどうしよう…」を考えていくことなのです。
事業経営者による労働者の搾取

アダム・スミス亡き後、19世紀には早くも「資本主義の道徳的条件」が満たされない時代がやってきます。
事業経営者が、利潤を稼ぐことだけを追い求め、労働者をこき使うようになるからです。
そこでは、現代のブラック企業ですら真っ青の、劣悪な環境、低賃金での長時間労働が当たり前に行われていたようです。
ポイントは、この状況において「資本主義の道徳的条件」の①と③が成立しなくなっていることです。
- 自由競争市場がフェア・プレイに則った競争の場であること、特に資本を動かす人間がフェア・プレイを意識する人間であること
- 資産を事業に活用するのではなく、貸し出して利益(利子・地代)を得ようとする場合、その行動が資産をよい用途に向けていく助けになり、全体の富裕化を促進すること
- 強者が弱者を支配せず、相互利益の関係を結び、弱者の能力も活かさせること
というのも、資本を動かす人間、つまり事業経営者がフェア・プレイではなく利潤だけを追い求め、労働者という弱者を搾取しているからです。
そこで、この状況への対処を考えたのが、19世紀の経済学者J・S・ミルとマーシャルでした。
2人の思想の共通点は、事業経営者のあるべき姿を提示したことです。
J・S・ミル
J・S・ミルは、事業経営者は労働者への分配(フェアな扱い)した方が良いと主張しました。
利潤で私腹を肥やすだけではなく、労働者への給与や労働環境へ配分することで、結果的に労働者の生産性は上がるからです。
働き方改革が叫ばれる昨今こそ当たり前の考え方ですが、当時としてはとても目新しい主張だったに違いありません。
ちなみに、労働環境の改善による労働者の生産性向上という考え方は、國分功一郎著『暇と退屈の倫理学』において、自動車メーカー「フォード・モーター社」の例が挙げられていました。
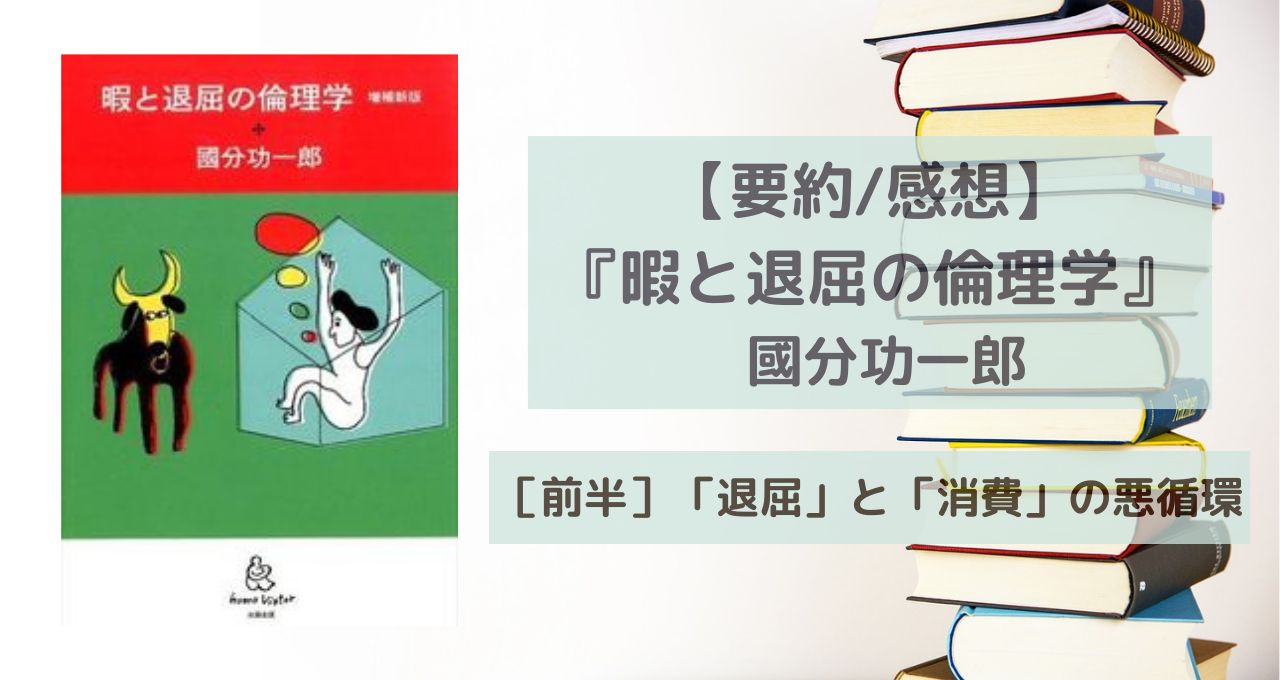
『暇と退屈の倫理学』では、適度な余暇による労働生産性の向上で事業経営者の利潤が最大化される、つまり余暇すら資本主義に組み込んだ、という否定的な側面に着目していました。
一方で、ミルの主張は、賃金アップや労働環境の改善といった労働者へのフェアな扱いは、各自の能力を伸ばすといったプラスの側面を捉えたものです。
マーシャル
ミルの少し後の時代に生まれたマーシャルも同様に、事業経営者のあるべき姿を提示しようとします。
まずマーシャルは、企業の成長とは、労働・資本・土地に加えて「組織」という要素が重要である、と主張します。
企業の活気・雰囲気・態度といったものは、その企業の知識・技術の成長を助ける無形の資本であるからです。
これは現代を生きる私たちにも想像に難くない考え方です。
今でいえば企業の「社風」とも言うべきこの要素は、資本力とは別の要素として確かにその企業の成長要因となり得ます。
そして、マーシャルは「組織」を活気ある状態にするためには、事業経営者の「経済騎士道」が重要であるとします。
「経済騎士道」とは、目先の利益にとらわれず、中世の騎士のように誇り高く、名誉を重んじた行動を取るべきという倫理のことです。
つまり、端的にいえば「成長のためには人望のある事業経営者になり組織を活気づけなさい」ということです。
このようにして、ミルやマーシャルは、事業経営者の利潤動機は否定せず、「フェアプレイ」の制約の中に置くことで、崩れてしまった「資本主義の道徳的条件」を回復させようとしたのです。
「金融」による「産業」の阻害

しかしその後、事業経営者がいくら「経済騎士道」を持っていても、解決できない問題が生じてきます。
それが、「金融」の力です。
20世紀のイギリスの経済学者、ジョン・M・ケインズは、金融に関わる「投資家」と産業に関わる「企業家」が対立関係にあると捉えます。
ミルやマーシャルの時代は、「企業家」(事業経営者)と「投資家」という区分が曖昧であり、「よいお金儲け」のためには、「企業家」がフェア・プレイの精神を持つべきと考えました。
しかし、20世紀のイギリスでは、「投資家」と「企業家」が明確に分かれ、「投資家」の行動は利回りの高い対外投資に向かってしまい、資本が国内の「企業家」へまわらない状況に陥ります。
「企業家」が「よいお金儲け」をするかどうかという問題の前に、そもそも適切なところに資本が投入されないということです。
ケインズは、この状況を踏まえ、「金融」という仕組みが「産業」を邪魔していると考えるようになります。
株式市場は「美人投票ゲーム」
このことは、私たちにとっても馴染み深い「株式会社」を例に考えると、非常に分かりやすくなります。
株式会社においては、会社を動かしている「事業経営者」と、会社の所有者である「株主」が明確に分かれます。
このような「所有と経営の分離」は、株式市場のおける「美人投票ゲーム」を引き起こすとケインズは考えました。
・参加者は100枚の写真から最も美しい6人を選ぶ
・選んだ6人が全参加者の平均的な好みに最も合致した人が勝ち
→自分が選んだ6人が、全体投票の1位~6位に合致していれば良い
別に「美人投票」以外でも例は示せたんじゃないかと思いますが、ケインズは「美人投票ゲーム」をやりたかったのでしょうか、、
それはさておき、このゲームのポイントは、自分が美人と思う人に投票するのではなく「みんなの票がどこに集まるとみんなが思うか」を予想することです。
つまり、参加者の実際の意見とは別のところで、得票率が決まるという点です。
そしてケインズは、株式市場も同じようなことが起こっている考えます。
本来であれば「収益性が高く将来性のある有望な事業を行う会社の株価が上がり、そうではない会社の株価は下がる」ことが、結果的に最も公共の利益に繋がります。
しかし、実際には「どの企業の株価が上がるとみんなが考えるか」を予想するゲームとなっているわけです。
株式投資におけるテクニカル分析は、会社の財務状況や業績を鑑みずに、ローソク足や移動平均線から株価を予測するという、まさに予想ゲームであることを前提とした手法です。
こうした状況は、「事業経営者」の経営にも影響を与えます。
投資家に「今後もこの会社の株価は上がるだろう」と思ってもらうために、長期的な利益ではなく一時の高株価を演出するための戦略に終始してしまう可能性があるからです。
ケインズ政策
このようにケインズは、「金融」の仕組みが「よいお金儲け」を妨げてしまうと考えました。
そこで、金融=所有者の利益追求を抑え込むため、政府が積極的な役割を果たす必要性を主張します。
ケインズが示す処方箋は、資本主義経済をまちがった方向に歪める「金融=所有者の利益追求」の力を抑え込み、「産業=価値を生み出す活用による利益追求」が自由競争経済の下でその潜在的な力をフルに発揮できるようにすることであった。
そのためには、貨幣を自らの手で管理して利子率を下げなければならない。外から借金取りに脅かされ、国内産業を犠牲にするようなことがないように、国際的な制度が必要である。また、貯蓄超過による需要不足に、さまざまな政策を講じてマクロ的に対処しなければならない。
中村隆之『はじめての経済思想史 アダムスミスから現代まで』講談社現代新書
こうした必要性を実現しようとしたのがいわゆる「ケインズ政策」に他なりません。
政府による介入を肯定するケインズは、アダムスミスの自由放任主義を否定していると捉えられがちです。
しかし、実はアダム・スミスの道徳的条件を20世紀前半の現実において満たそうとしたものであり、ケインズもまた「経済思想の本流」に位置付けられのです。
終わりに
今回は、アダム・スミスを軸とした「経済思想の本流」を紹介してきました。
本書を読むと、経済学者たちは、いかに資本主義経済と向き合い、折り合いをつけるために苦闘してきたかが分かります。
社会学や哲学は、資本主義を斜めから見るようなスタンスである一方、経済学は名前の通り資本主義という現実に正面から切り込んでいく学問であると感じます。
そういった意味では、資本主義が広く受け入れられた現代において、経済学部こそ文系の花形であるというのは必然なのかもしれません。
本書では、今回紹介した以外にも、私有への批判という形で経済学への重要な示唆を提示したマルクスや、「経済思想の本流」以外の思想としてハイエクやフリードマンといった著名な経済学者が紹介されます。
経済学への入門としてぜひ読んでみてください。