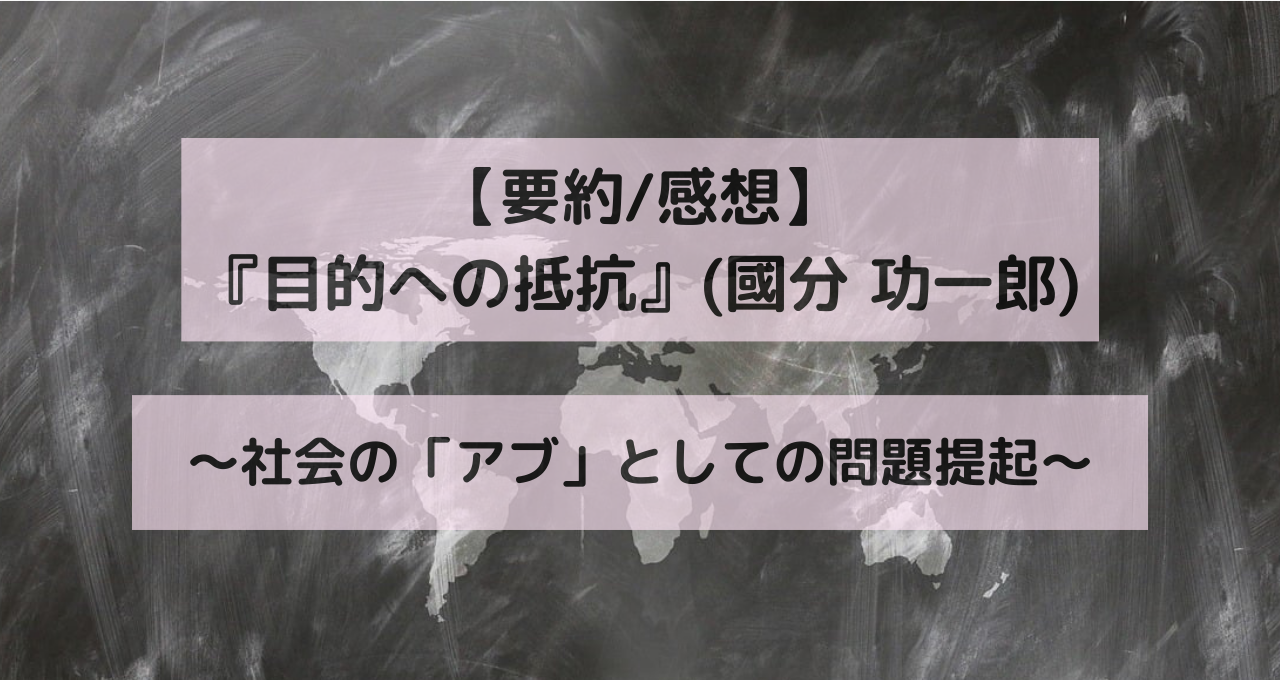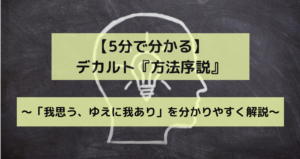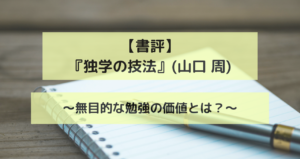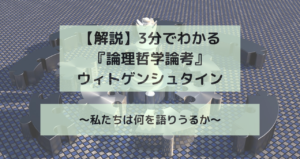今回紹介するのは、國分功一郎著『目的への抵抗―シリーズ哲学講話―』
新型コロナウイルス流行を経て、國分が感じた社会への違和感。
その違和感を語った2つの講演がおさめられているのが本書『目的への抵抗』です。
多くの人が言い出すほどではない、しかし確実に感じていたであろうその違和感が、見事に言語されていると感じます。
そして本書は、國分功一郎のベストセラー『暇と退屈の倫理学』の続編でもあります。
今回は、そんな本書の内容をざっくりと紹介します。
ぜひ最後までお付き合いくださいませ。
『暇と退屈の倫理学』の記事も上げているのでぜひ併せてご覧ください。
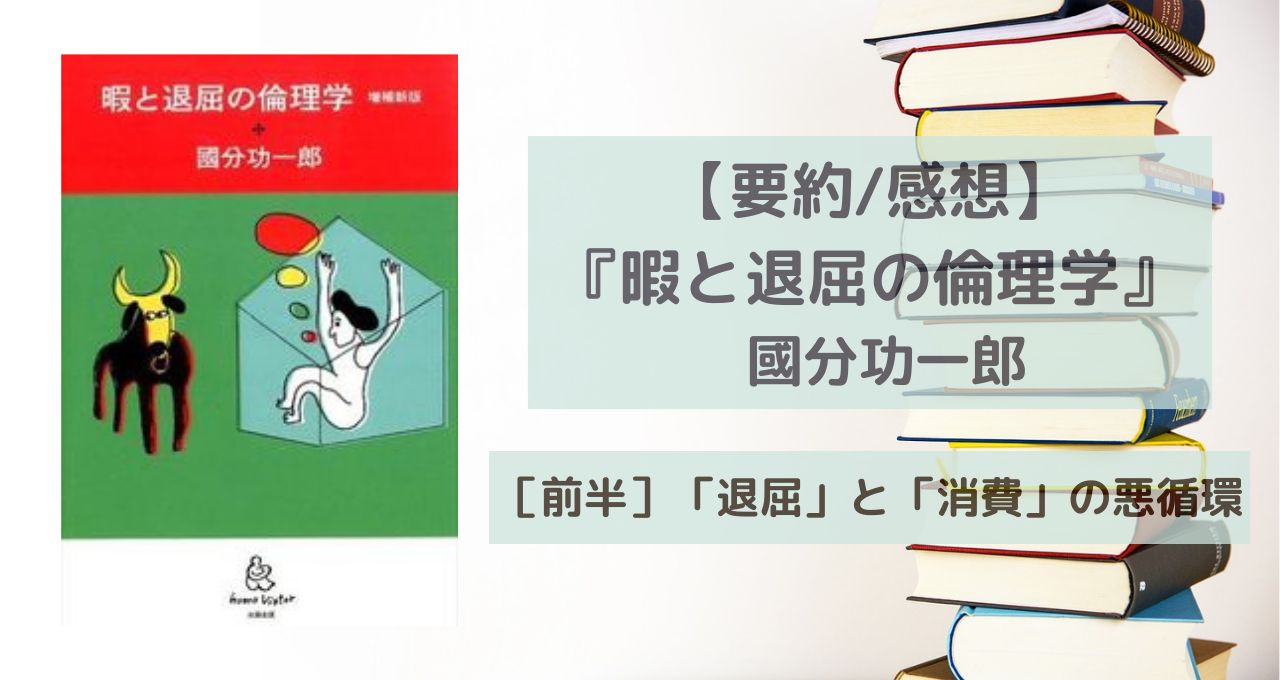
『目的への抵抗』はどんな本?
ベストセラー『暇と退屈の倫理学』は、もともと哲学に関心の薄い層にも國分の名前を知らしめた1冊です。
他にも、『スピノザ 読む人の肖像』『はじめのスピノザ 自由へのエチカ』など、スピノザの研究に関する著作なども有名です。
國分功一郎は、どの著作も基本的に平易な語り口で読みやすいため、私みたいな哲学専攻でもない普通の人からすると、とてもありがたい存在です。
特に本書は、学生向けに行われた2つの講義をまとめたものです。
よって、教育者として語りかけるような口調で明快な議論を進めていくため、とても読みやすい内容になっています。
『目的への抵抗』の構成
本書は、それぞれの講義内容とその質疑応答がまとめられた、第一部、第二部に分かれています。
第一部 哲学の役割ーコロナ危機と民主主義
⇒2020年10月2日「東大TVー高校生と大学生のための金曜特別講座」の講義内容
第二部 不要不急と民主主義ー目的、手段、遊び
⇒2022年8月1日「学期末特別講話」と題する特別授業の内容
最初の講義はコロナウイルス発生から1年も経っていない頃ですね。
そして、2つ目の講義は、日本においては第7派の真っ最中と、コロナ危機が社会な甚大な影響を与えていた時期だったようです。
それぞれに共通する主題は、コロナ危機において國分が感じた社会への問題提起です。
1つ目の講義と2つ目の講義との関連はもちろんのこと、2つ目は『暇と退屈の倫理学』の議論とも結びつき、とても興味深い議論が展開されていきます。
それでは、早速その内容を見ていきましょう。
第一部 哲学の役割ーコロナ危機と民主主義

第一部で取り上げられるのは、イタリアの哲学者であるジョルジョ・アガンベンの問題提起です。
この問題提起については、本書における説明を引用します。
アガンベンは、コロナウイルスのの拡大を防ぐという理由で実施されている緊急措置は、「平常心を失った、非合理的で、まったく根拠のないものである」と指摘し、イタリア学術会議という専門家集団の声明を引用しています。その声明によれば、「集中治療室への収容を必要とするのは患者の四%のみという計算になる」。にもかかわらず、「激しい移動制限」が行われ、「正真正銘の例外状態」が引き起こされている。つまり、「根拠薄弱な緊急事態」を理由に、甚大な権利制限が行われている。アガンベンはこのように現状を鋭く批判しました。
國分功一郎『目的への抵抗』新潮新書
これは、2020年2月26日にイタリアの新聞に掲載された「根拠薄弱な緊急事態によって引き起こされた例外状態」というタイトルの論考です。
2020年2月26日といえば、丁度イタリアでは最初の感染拡大が起こり、死者が発生し始めた時期です。
そういった状況の中で、アガンベンのこの指摘は、国内外問わず多くの批判を浴びたのは想像に難くありません。
しかし、もちろん新聞に掲載される以上、多くの批判がなされることは承知の上でしょう。
それでも伝えたいことがアガンベンにはあった。
いったいそれは何なのでしょうか?
哲学者の役割とは?
ここでアガンベンの主張の前に、第一部のタイトルにもなっている「哲学の役割」についての本書の言及を紹介します。
本書では、哲学の役割は「社会の虻(アブ)」であると著者はいいます。
これは、古代ギリシャの哲学者プラトンの『ソクラテスの弁明』から持ってきた言葉です。
私は神によってポリスにくっ付けられた存在なのです。大きくて血統はよいが、その大きさゆえにちょっとノロマで、アブのような存在に目を覚まさせてもらう必要がある馬、そんなこのポリスに、神は私をくっ付けられたのだと思うのです。その私とは、あなた方一人ひとりを目覚めさせ、説得し、非難しながら、一日中どこまでもつきまとうのをやめない存在なのです。
プラトン(納富 信留訳)『ソクラテスの弁明』光文社古典新訳文庫
こちらは、私が読んだ光文社古典新訳文庫の『ソクラテスの弁明』から引用してきました。
この部分は、裁判にかけられたソクラテスが、哲学者としての自分の役割を語る部分です。
つまり、哲学者とは、社会(ポリス)という大きな馬にとって、時おりチクっと刺して目を覚まさせるような存在だということです。
これは言い得て妙だと感じました。
社会の人々にとって、「蜂」ほどの危険性はもたらさない、しかし「蚊」ほど些細な存在でもないという「虻」だというわけです。
そして、そのように考えるとアガンベンの主張の意図が見えてきます。
つまり、アガンベンはコロナ危機化において、人々を目覚めさせようとしたわけです。
それではいったい私たちは何から目覚めるべきなのか?
生の経験の分割
アガンベンの主張の背後にある1つ目の主題は、「生」に関するものです。
コロナ危機化において、感染拡大を防ぐことが至上命題である、という価値観は当たり前でした。
経済活動や教育、他者との交流は控えて、とにかくステイホームで感染を広げないことが求められました。
しかし、アガンベンは「生存のみに価値を置く社会」に対する疑問を投げかけます。
ここでいう生存とは、ただ単に生きていること、つまり「身体的な生の経験」です。
しかし本来「生」とは、「身体的な生の経験」だけではありません。
人間が人間として生きていることには、「身体的な生の経験」に還元されない「精神的な生の経験」があります。
ただ単に生きているだけではなく、安心して暮らせるとか、自由に暮らせるとか、そういった人間らしく生きていく経験のことです。
本来この2つは切り離せないないものですが、現代では「身体的な生の経験」だけを取り出して語られる世の中になったとアガンベンは指摘します。
コロナ危機下においては、皆が感染せず生き延びること、つまり人々の「身体的な生」が最優先とされました。
だからこそ「甚大な権利制限が行われ」、人間が人間らしく生きるという「精神的な生」を蔑ろにされているのでは?というのがアガンベンの言いたいことです。
- 生存、ただ単に生きていること
- コロナ危機において優先された
- 人間が人間として生きていること
- コロナ危機において甚大な権利制限
もちろん、これを「コロナが爆発的に流行しても何ら緊急措置を取るべきではない」という主張だと捉えるべきではありません。
生存のみを取り出しそれをことさら重大に持ち上げることに、何ら疑問を感じない私たちを、「虻」としてチクりと刺そうとしたわけです。
行政権と立法権
コロナ危機下では多くの国で、やむを得ない緊急措置として、政府が様々な自由の制限を行使しました。
本書で重要性が説かれている「移動の自由」についてもその1つです。
アガンベンはこの点から、行政権が立法権を凌駕することの危険性を指摘します。
本来行政権とは、法律によって定められた業務を行う機関であり、立法によって定めた法律の行使者でしかありません。
しかし立法権には、法律は一般的な内容を定めることしかできない、という限界があります。
法律が一般的な内容であるならば、そこに解釈の余地があります。
だから個別的な内容は現場、つまり行政の担い手が決定することになります。
そして、行政側からすれば、その解釈の幅が広いほどスピーディーで柔軟な決定が可能となります。
会社が営業ルールを定めたとしても、ある程度は現場の裁量に任せなければ仕事が進まないのと同様です。
しかし、それが度を超えて、立法権の管理を逃れてしまう状態を「例外状態」といいます。
例外状態の極端な例がナチスドイツです。
ナチスドイツの全権委任法は、「政府という行政機関を立法機関にした」法律です。
つまり、行政権が立法権を飲み込んだということです。
そして、コロナ危機下でも緊急事態を理由として、この例外状態が当たり前に受け入れられてしまった。
そのことをアガンベンは何としても指摘したかったのでしょう。
第二部 不要不急と民主主義ー目的、手段、遊び

第二部の議論は、コロナ危機の際の繰り返し用いられた「不要不急」という言葉からスタートします。
今こそ耳にする機会は減ってきましたが、「不要不急の外出を避ける」といった言葉は、コロナ危機下のスローガンといっても過言ではありませんでした。
そして、このスローガンのもとに観光や外食、イベントなど、「不要不急」とされたものは、当たり前のように排除されていきました。
しかし、著者はコロナ危機において、「不要不急」の排除がすすんで受け入れられたのは、もともと現代社会の傾向が顕在化した結果に過ぎないのではないかと主張します。
その現代社会の傾向について著者は以下のように言っています。
現代社会はあらゆるものを目的に還元し、目的からはみ出るものを認めようとしない社会になりつつあるのではないかーこれが今日の話で皆さんと共有したいと思っている問題です。消費社会の論理は二十一世紀になった現在でも支配的であるけれども、他方で、すべてを目的に還元する論理がそれと共犯関係を結んでこの社会を覆いつつあるのではないか。
國分功一郎『目的への抵抗』新潮新書
消費社会の論理 ー『暇と退屈の倫理学』より
ここでの「消費社会の論理」とは、『暇と退屈の倫理学』での消費と浪費の考察のことです。
ここでようやく本書と『暇と退屈の倫理学』が結びついてくるわけです。
著者は『暇と退屈の倫理学』において、哲学者・社会学者のボードリヤールの消費と浪費の違いを参照しました。
浪費・・・必要以上の物を受け取る、限界がある
消費・・・観念や意味の消費、限界がない
例えば、美味しいご飯屋さんで限界まで食べようとするのは浪費です。
しかし、インスタに載せる、友達に話すために流行のご飯屋さんに行くのは消費です。
そこで消費されるのはご飯ではなく、「今流行りのあの店に行った」「テレビで紹介されたあの料理を食べた」という観念です。
流行りが移り変われば、また別のお店に行くということを繰り返します。
観念の消費には、浪費おけるもうこれ以上食べれないという限界もなく、だからこそ満足がありません。
消費社会は、こういった満足のもたらさない消費を喚起し、「退屈が消費を促し、消費が退屈を生み出す」という悪循環を引き起こす。
だからこそ、観念ではなくそのものを受け取れる浪費で贅沢を取り戻そう。
それが『暇と退屈の倫理学』で提示された退屈への処方箋でした。
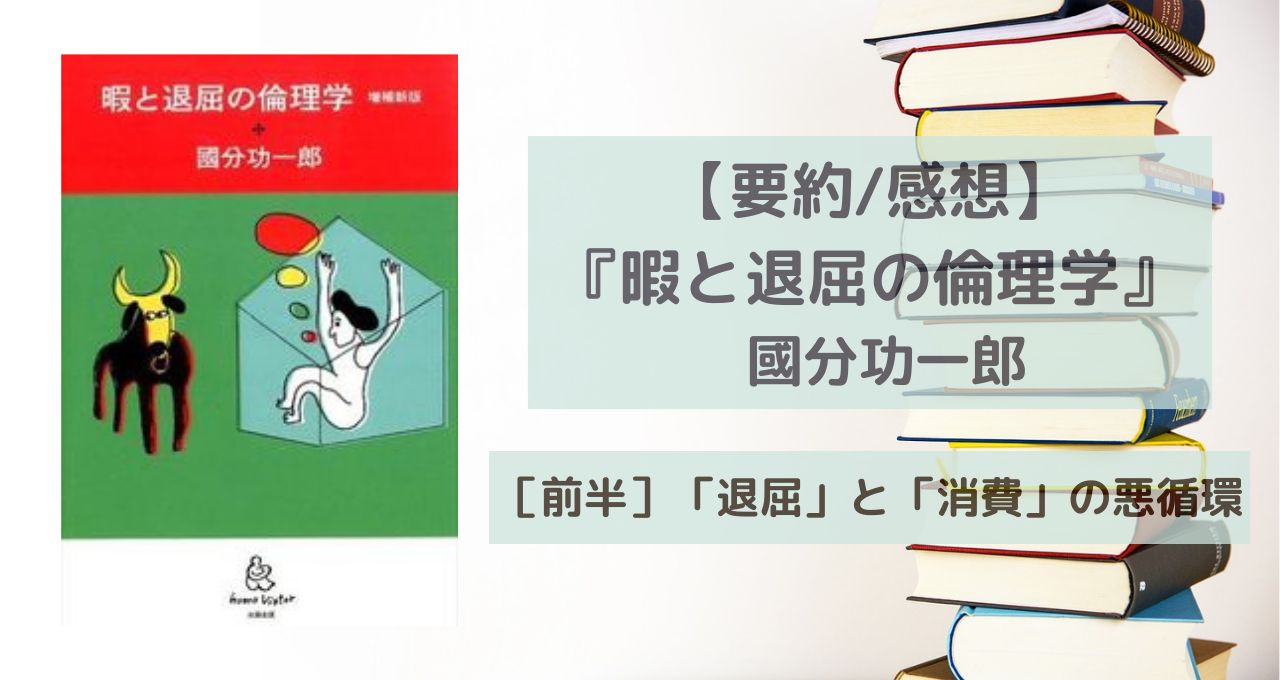
目的からの逸脱
贅沢であるとは、浪費することである。
これに加えて本書では新たな視点が加わります。
それが浪費と目的の関係です。
著者は、浪費には目的からの逸脱があると指摘します。
例えば、食事とは本来、栄養摂取という目的のための行為です。
しかし、それでたとえ栄養摂取は問題ないとしても、毎日カロリーメイトを食べることを贅沢とは言いません。
ということは、贅沢な食事というのは、栄養摂取という目的に還元できない側面があるということになります。
楽しんだり浪費したり贅沢を享受したりすることは、生存の必要を超え出る、あるいは目的からはみ出る経験であり、我々は豊かさを感じて人間らしく生きるためにそういた経験を必要としているのです。必要と目的に還元できない生こそが、人間らしい生の核心にあると言うことができます。
國分功一郎『目的への抵抗』新潮新書
すべてを目的に還元する論理
著者は、先ほどの問題提起にて「すべてを目的に還元する論理」と「消費社会の論理」の共犯関係という言葉を使っています。
これはどういうことでしょうか?
このことをもう少し具体的に述べているのが次の部分です。
そもそも、なぜ消費が浪費と混同されてしまうのでしょうか。それは消費社会が必死に「消費こそが贅沢をもたらすのだ」と消費者を説得し続けているからでしょう。だからこそ消費社会は、贅沢に気づき始めた人間には、「必要や目的を超えて何かを求めるなんておかしいでしょ」とまるで倫理を諭すかのようにささやいてくる。
國分功一郎『目的への抵抗』新潮新書
限界のない消費を促すことによって拡大してきた消費社会にとって、皆が浪費という贅沢の可能性に気づき始めるのは困るわけです。
そこで、都合が良いのが「すべてを目的に還元する論理」です。
なぜなら、浪費という贅沢を戒める非常にもっともらしい理由になるからです。
目的の概念
本書はここから「目的」という言葉をより深堀りしていきます。
ここで著者は、ハンナ・アーレントの目的の概念を参照します。
アーレントは、「目的によって手段が正当化される」という手段と目的の関係を指摘します。
ここで面白いのが、「目的によりしばしば手段が正当化される」のではなく、そもそも目的の概念には手段の正当化という要素が含まれると言っていることです。
つまり、手段を正当化しない目的は存在しないということです。
そして、さらに進んでアーレントの『全体主義の起源』からの引用も非常に興味深い。
全体主義の支配者にとっては、チェスも芸術もともにまったく同じ水準の活動である。双方の場合とも人間は一つの事柄に没入しきっており、まさにそれゆえに完全には支配し得ない状態にある。
アーレント『新版 全体主義の起源 3-全体主義』
ここでのチェスと芸術は、何らかの目的のためになされることではなく、それ自体が楽しくそれ自体のために行なうことの例として挙げられています。
つまり、支配のためには、”いかなる場合でも「それ自体のために或る事柄を行なう」ことの絶対にない人間”でなければならないということです。
ブラック企業が求めるのは、実は仕事自体に楽しみを見出すような人ではなく、会社利益という目的のためのどんな犠牲を払ってでも粉骨砕身働く人なのです。
消費社会の徹底
しかし、現代社会において、このように目的のために行動する人間の価値は非常に高いという風潮があります。
「目的のために一生懸命に動く人間こそ理想的」だという意見に反対する人はそう多くはないでしょう。
こういった人間像は、消費社会の徹底の末に生まれてくると著者は言います。
食事に例に戻ると、「消費の食事」と「浪費の食事」は次のような違いがあります。
- 目的:インスタにアップ、友達に話す
- 手段:美味しいご飯屋さんで食べる
- 目的:食事を楽しむこと
- 手段:美味しいご飯屋さんで食べる
消費においては他の目的があり、その手段として食べることがあります。
つまり、消費は何らかの観念を目的とした手段として行われるのです。
だからこそ、消費社会が支配的な現代において、”いかなる場合でも「それ自体のために或る事柄を行なう」ことの絶対にない人間”の価値は高いとされるわけです。
自由について
さらに、ここからは「自由」という概念に踏み込んでいきます。
ここでも著者は、アーレントの自由に関する定義を参照します。
アーレントが言っているのは、行為にとって目的が重要な要因であることは間違いないが、しかし行為は目的を超越する限りで自由なのだということです。
國分功一郎『目的への抵抗』新潮新書
目的を超越するとは、行為そのもの自体に楽しみや価値を見出すことです。
たとえば、目的地を決めていたとしても、ドライブ自体が楽しいと思えるなら寄り道の自由があります。
しかし、ドライブは目的地到着のための手段でしかないのであれば、最短経路以外の自由はなくなるわけです。
そして、こういった合目的的活動から逃れる営みを、本書では「遊び」に見出します。
そのもの自体に没頭し遊んでいるとき、それは目的と手段の連関から逃れている瞬間に他なりません。
目的への抵抗
こうしてコロナ危機における「不要不急」という言葉から出発した議論は、消費社会の論理、目的、自由といった概念を経由してきましたが、この旅路の結論はとても明快です。
目的のために手段や犠牲を正当化するいう論理から離れることができる限りで、人間は自由である。人間の自由は、必要を超え出たり、目的からはみ出たりすることを求める。その意味で、人間の自由は広い意味での贅沢と不可分だと言ってもよいかもしれません。そこに人間が人間らしく生きる喜びと楽しみがあるのだと思います。
國分功一郎『目的への抵抗』新潮新書
現代社会において、「目的を常に意識して無駄を排する人間」は理想的であり一定の価値を置かれています。
そして、目的合理的な行動、意思決定の重要性を説く言説は巷に溢れています。
しかし、國分功一郎は、現代社会に生きる私たちをチクりと刺す「虻」として、「自由による目的への抵抗」を主張します。
私たちは、あらゆるものが目的合理性に還元されてしまう事態に警戒しなければなりません。
目的からの自由を忘れたとき、目的のためにあらゆる手段・犠牲を正当化する社会が訪れてしまうからです。
終わりに
今回は、『目的への抵抗』のあらすじを紹介してきました。
本書は、目的を絶対とする(ように感じられる)社会への、私自身の違和感を見事に言語化してくれていると感じました。
「なんで○○したの?」
「そこにどんな意義があるの?」
「それって役に立つの?」
私たちが意思決定を行うとき、世間から囁かれるのはこのような言葉です。
何かをするには、目的が設定されていて、その目的に対して合理的でなければならないからです。
しかし、人間が人間らしく生きる喜びと楽しみとは、目的を超越し自由になることでした。
目的は重要ですが、そのために自分自身の犠牲を強いるのではなく、そのもの自体を楽しめる人間になること。
このことを常に忘れないようにしたいですね。